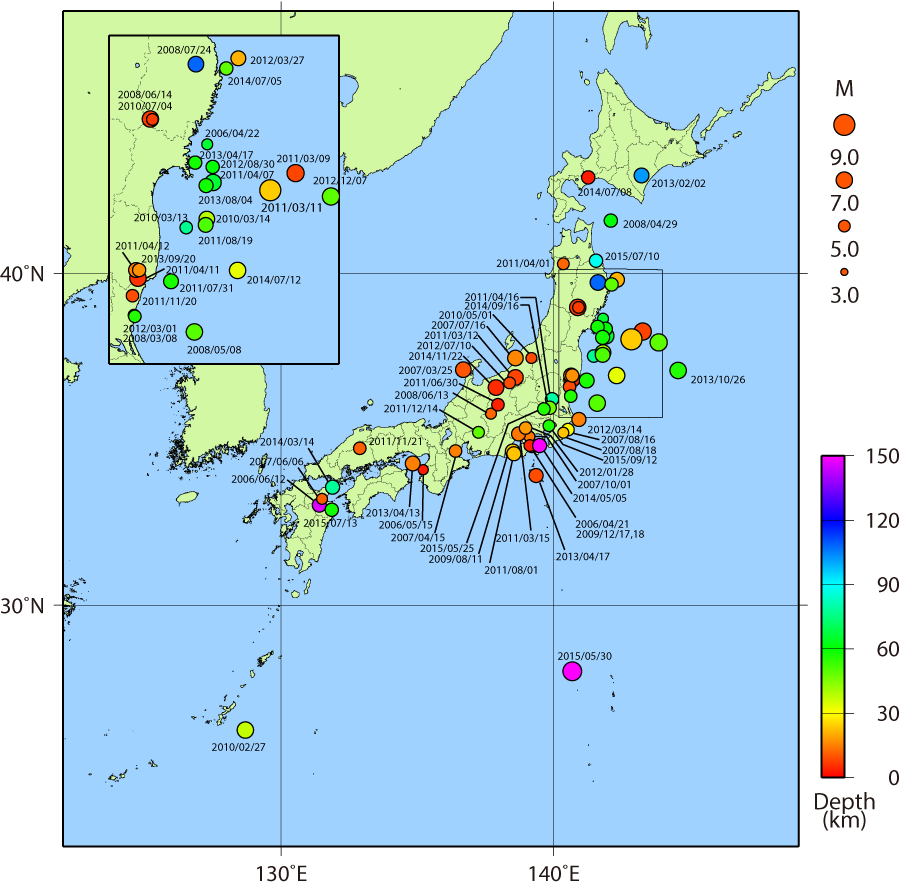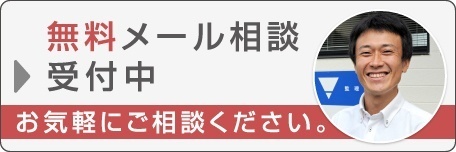鳥の糞にお悩みですか?
category : 改修工事
鳥の糞に悩まされているマンションオーナー様からお電話いただき、専門業者と一緒に調査に立ち会いました。
最上階のエレベーター機械室の屋根が真っ白に。。。

糞の正体は『カワウ(河鵜)』だそうで、マンション横を流れる川の魚を棟屋から狙っているとのだとか!
オーナー様も何十年も経つマンションで初めての被害に困惑されていました。
後日、工事に取り掛かることに。

剣山のようなトゲトゲを周囲に張り巡らせ、鳥が留まれないよう対策します。